
- レーベン水戸 THE PREMIERE トップページ >
- LOCATION
※現地付近の空撮(2015年6月撮影)にCG処理を施し加工したもので、実際とは多少異なる場合がございます。
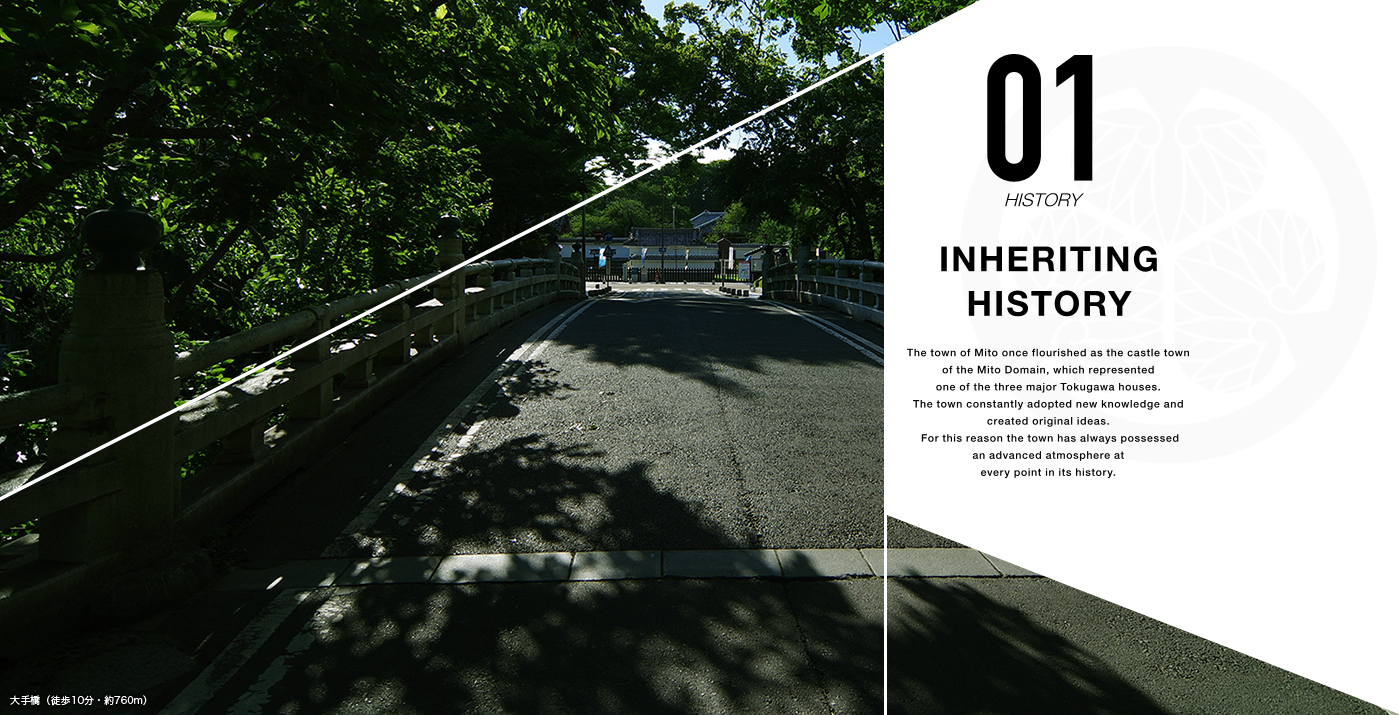
古代から人々は海や川の出入り口を『みと』または『みなと』と呼んでいました。北に那珂川、南に桜川・千波湖を望み、船運の戸口とされていたこの場所も、いつのころからか『水戸』呼ばれるようになりました。『水戸』の町としての成り立ちは、平安時代の末期、常陸大掾の一族であった馬場小次郎資幹が、今の水戸城跡に邸をかまえたことに始まるといわれています。その後、那珂川の船運と、豊かな水と肥えた土地に広がった稲作を主要産業として常陸国の中心地として栄え、江戸時代の徳川氏の治政へと繋がっていきます。縄文時代のものとみられる大串貝塚などが市内でも発見されており、この地が、古より現代にいたるまで、豊かな水と確かな大地に恵まれ、人々が暮らしていくことに適した場所であったことがうかがえます。
関ヶ原の合戦を経て1609(慶長14)年、徳川家康公の第11男・頼房公が水戸城主となり、水戸は徳川御三家の一つである水戸徳川家の城下町として、関東では江戸に次ぐ城市として整備されました。現在の水戸市の原型が造られたのはこのころです。第2代藩主の徳川光圀公の時代に、飲料用水や街道が整備され、藩政の基礎が固まりました。
明治以降、1871(明治4)年の廃藩置県と県の統廃合を経て茨城県の誕生後、水戸には県庁が置かれ、茨城県の中心として歩むこととなりました。1889(明治22)年、市制町村制と同時に全国31市の一つとして「水戸市」が誕生。1989(平成元)年には市制施行100周年を迎え、記念事業として水戸芸術館がオープンするなど、現在は文化都市として発展にも注力しています。
